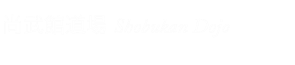日本剣道の歴史
日本の剣道の歴史については、大和尊命が「天」「地」「人」の三段の位を定めたのが、その起源であるとされている。
 日本では太古以来、大和民族の尚武精神と相まって、多数の武器の中で刀剣が最も尊重され、神聖視されていたことは疑いもないことである。
日本では太古以来、大和民族の尚武精神と相まって、多数の武器の中で刀剣が最も尊重され、神聖視されていたことは疑いもないことである。
剣の用法に対する名称が文字に表された最初のものは、『日本書紀』崇神天皇四十八年の条に、「皇了豊城入彦命が八廻撃刀す」とあるのがそれで、上代時代には「たちがき」という名称で呼ばれていたようである。当時の剣法は言うまでもなく、実戦で相手を倒すことが主眼であって、後世のように一定の形があったわけではないが、その用法も熱心に研究工夫されていたことと思われる。
大化改新の頃、桓武天皇が都を京都に定められたさい、大極殿を建て、武人は平常ここで武芸を練り、また毎年五月五日には、桓武天皇をはじめ平安朝歴代の天皇が武芸を御覧になることが慣例となり、武人はこの天覧試合に出場するのが一代の光栄となった。
この勝負は、「尚武」=「菖蒲」に通じ、五月五日の武家の軒を飾る菖蒲の節句の縁起はここにあると言われている。
室町中期以後、世は戦国乱世となり、自守自衛のため、あるいは立身出世のため、武人ばかりでなく一般人も競って武術を身につけようとしたので、剣法は隆盛の一途をたどった。この時代になって、剣法としての組織的な体系が形づくられ、剣法の師範家というようなものが生まれて『師授伝習』が行われるようになり、諸種の流派が生まれるに至った。
当時の諸流派のうち、源流として最も代表的なものは、飯篠山城守家直の天真正伝神道流、愛洲移香斎の陰流、中条兵庫頭長秀の中条流、の三つの流派である。
天真正伝神道流の流れには、塚原卜伝の「卜伝流」、諸岡一羽の「一羽流」、根岸兎角の「微塵流」、瀬戸口備前守の「自源流」などがある。
又、陰流からは、上泉武蔵守の「新陰流」「疋田陰流」「柳生新陰流」等の流派が生れ、中条流からは「富田流」、鐘捲自斎の「鐘捲流」、が出現した。中でも伊藤一刀斎の「一刀流」は、この流派での最も有名なものである。
そして江戸期に入り、「儒教」「仏教」「神道」の影響によって道徳的要素が加味され、武士の実戦道徳としての武士道と融合し、剣法に「精神的」「理論的」内容を与えたことも、この時代の著しい特微である。
直心影流の長沼四郎左衛門、一刀流の中西忠蔵等によって正徳年間(1711~1715)に剣道防具が開発され、竹刀で打突し合う「打込み稽古法」が確立された。従来の素面・素小手の組太刀による形の稽古から、防具を使用しての竹刀稽古への移行である。
「剣道」という名称が一般的に使われるようになったのは、明治半ば頃「剣道」がやや復興しかけてから以後のことで、明治時代は主として「撃剣」または「剣術」という名称が使われていた。
大正8年、大日本武徳会が各流派を統合することによって、「剣道」に名称が統一された。そして、日本刀による技と心を後世に継承すると共に、竹刀打ち剣道の普及による手の内の乱れや、刃筋を無視した打突を正したのである。竹刀はあくまでも日本刀の替りであるという考え方である。
戦後、日本剣道は抑圧されていたが、全国各地に剣道連盟が結成されるとともに甦った。しかし、それは竹刀競技としての剣道であり、今日も剣道は武道か?スポーツか?といった議論の的となっている事も事実であろう。